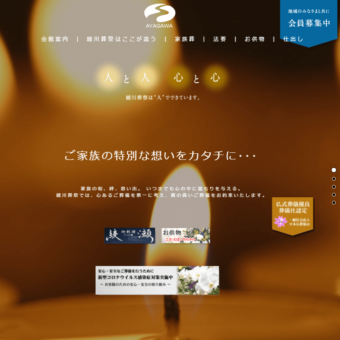葬儀の喪主による挨拶。使ってはいけない言葉や挨拶を考えるポイント

葬儀の挨拶は、喪主の重要な役割りのひとつです。その中でも告別式の親族を代表する挨拶は、しっかりとその思いを伝えたいものです。とはいえ、あわただしい中で挨拶文を考えるのは、そうたやすいことではありません。今回は葬儀にて挨拶を行う際に、使ってはいけない言葉や、挨拶を考えるポイントについてご紹介します。
喪主が挨拶を行うタイミング
葬儀は、お通夜、告別式、精進落としといった流れが一般的です。それぞれの場面で、喪主が挨拶をします。まずお通夜は、故人と関わりの深い家族、親族や友人たちが別れをしのぶ最後の夜です。開式になると、僧侶が入場します。読経と法話があり、焼香と続きます。
僧侶が退席してお通夜が終了するタイミングに、弔問客に向けて喪主が挨拶をします。挨拶の内容は、通夜参列のお礼と故人が他界したことの報告、生前のご厚誼についての感謝を延べ、最後に告別式の案内などを伝えます。お通夜が閉式した後に、通夜振る舞いを行わない場合は、会場の出口にて弔問客を見送りましょう。
通夜振る舞いとは、お通夜に参列した弔問客を食事などでもてなすこと。通夜振る舞いを行うか行わないか、その内容も、地域によって違いがあります。また最近は、お通夜、通夜振る舞いともに簡略化される傾向が見受けられます。
通夜振る舞いを行う場合は、開式の挨拶と、閉めの挨拶も必要です。開式では、開式に対するお礼と通夜振る舞いの案内が主な内容です。閉式の際は、通夜振る舞いの感想とお礼、翌日の葬儀の案内を再度行って、閉式の挨拶とします。いずれも、参列いただいたことに対しての感謝と気づかいの言葉を添えるとよいでしょう。
次に告別式です。おもなタイミングは、受付と出棺式の前です。告別式の基本的な流れは、まず僧侶をお迎えします。それから一般参列者の受付をはじめます。受付では、ごく簡単で構いませんので、参列の方々にお礼の気持ちを伝えましょう。告別式が始まると、僧侶による読経、弔辞や弔電の紹介、焼香、閉式と続きます。そして出棺時に、参列者一同に向けて、遺族を代表した挨拶を行います。故人との関係、故人が生前お世話になったこと、参列いただいたことに対するお礼と感謝の気持ちを伝えます。
最後に、精進落としの挨拶です。精進落としとは、火葬の後に、僧侶や各地から集まった親族や友人たち、お世話になった方々を労うために食事を用意して振る舞うこと。精進落としも通夜振る舞いなどと同じように、宗派や地域で違いがあり、時代による変化もあるようです。精進落としの挨拶は、会食をはじめる前と最後に行います。はじめの挨拶では、葬儀を滞りなく無事に終えられたことに対する感謝を伝えましょう。閉めの挨拶では、これでお開きになること、今後についての前向きな気持ちとお礼を伝えます。法要の日時が決まっているなら、この時に案内をします。
使ってはいけない言葉
葬儀の際に避けなければいけないのは、死や不幸が続くことを連想させる「忌み言葉」です。忌み言葉には直接的な言葉以外に、普段何気なく口にしてしまう言葉もたくさんあります。
まず不幸が続くこと、重なってしまうことを連想させる「重ね言葉」です。例として、重ね重ね、ますます、しばしば、わざわざ、いろいろ、次々、再三再四など、同じ言葉を重ねて使うのはよくありません。また、重ねて、再度、再び、次に、追って、といった言葉も、重ね言葉となります。このような言葉は、前後の文脈にあわせて言い換えます。一例として、「重ね重ね、重ねて」は「あわせて、加えて」、「ますます」は「末永く、一段と」となります。
生死に関する言葉の中でも、直接的なものは言い換えるようにします。一例として、「死亡」は「逝去(せいきょ)、他界」、「急死」は「突然のこと」、「生存中」は「生前」といった表現です。不吉とされる言葉や不幸を連想させるような言葉も、使ってはいけません。数字の「4、四」や「9、九」は代表的なものでしょう。忌み言葉は喪主の挨拶以外にも、葬儀会場での何気ない会話などでもうっかり使ってしまうことが想定されます。事前に心得て置き、使わないよう注意することが大切です。
挨拶を考える時のポイント
葬儀において、挨拶をする場面は数多くありますが、その中でも告別式での出棺前の挨拶は、特に慎重に行いたいものです。ここでは、挨拶を考える時のポイントをお伝えします。
まずは、自己紹介です。故人に対して自分がどういった立場の者なのかを最初に伝えます。次に、弔問の皆様へのお礼の言葉です。参列いただいたことへの感謝の気持ちを必ず伝えましょう。それから、生前の故人への厚意に対するお礼と続けます。ここで、故人にまつわる生前のエピソードを織り交ぜて紹介し、最後に今後について、残された家族へのお力添えをお願いして締めとしましょう。
基本的な内容や構成は定型文を元に、3分以内を目安に文面を組み立てるとよいでしょう。この中で、故人に関するエピソードだけは、自分で文面を考える必要があります。紙にまとめておいた挨拶文を読み上げても構いません。使ってはいけない言葉に気をつけて、故人の人柄が伝わるようなエピソードを用意しましょう。
葬儀にて使ってはいけない言葉や、挨拶を考えるポイントについてご紹介しました。死を悼む気持ちはみんな同じとしても、表す言葉次第で印象はずいぶんと変わるものです。お通夜、告別式、精進落としと、当日は気を抜けない場面が続きます。挨拶を考えるのも大変ですが、この記事がそんな時の一助になれば幸いです。故人への思いと参列者への感謝をこめて、温かな気持ちが伝わる挨拶にしたいものです。
■お坊さん不在の葬儀はだめなの?手配方法について紹介します
■葬儀の日取りはどうやって決めればいい?「六曜」は関係する?
■葬儀後の食事とは?「通夜振る舞い」「精進落とし」について
■葬儀の案内状はどうやって書くの?書き方やマナーについて紹介