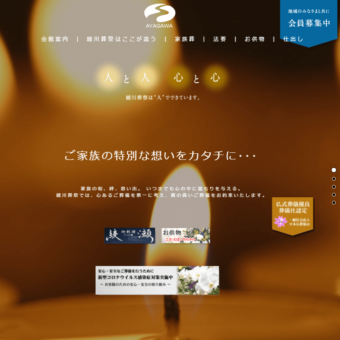葬儀の様子を写真に撮ってもいい?撮影時のマナーを確認しよう!

葬儀の様子を写真撮影している人を見て、マナー違反じゃないの?と感じた方もいるのではないでしょうか。そもそも、葬儀の様子を写真に残すことは許されることなのか気になりますね。今回は、葬儀の写真撮影について、行ってもよいのか、行う場合のマナーなどをまとめてみました。
そもそも葬儀の様子を写真に撮ってもいい?
葬儀の写真撮影は、基本的に問題ありません。しかし中には、どうして写真撮影するの?と疑問に感じてしまう人もいるでしょう。葬儀の写真を撮る理由は何なのでしょうか。
故人との思い出を残したい
葬儀は、故人とのお別れの場です。最後に一緒に過ごせる時間でもありますね。そのため、思い出として残しておきたい、後で振り返りたいという理由から、写真撮影される人もいるのです。
参列された人にも思い出して欲しい
葬儀に参列された方にも、振り返ってもらいたいという想いで撮影されている場合もあります。参列して頂いたお礼状を出す際に、写真を添えて送るということもあるようです。
集合写真を撮影したい
葬儀では、なかなか集まることがない親族が集まりますね。そのため、親戚との集合写真として撮影される人もいます。故人との思い出だけでなく、親戚の思い出として残すことができます。
参列者は撮影できるのか?
葬儀の写真は、親族であれば撮影しやすいものですが、参列者となると撮影してもよいのか悩むところでしょう。これは、遺族に写真撮影をしてもよいかどうか確認してから行うようにしてください。葬儀場が、撮影禁止となっている場合もありますし、遺族が写真撮影に対してあまりよい印象を持たれない場合もあります。勝手に撮影することだけはやめましょう。
葬儀で写真撮影をする際の基本的なマナー
葬儀場で写真撮影をする際には、マナーを守って行いましょう。基本的なマナーをまとめておきます。
葬儀場に確認する
葬儀の写真を撮影する場合は、葬儀場の担当者に写真撮影をしてもよいかどうか確認してください。写真撮影が可能となった場合でも、可能とされる範囲について確認してから撮影しましょう。
遺族に確認する
遺族が撮影する場合は、葬儀場の許可を得られれば問題ありませんが、参列者が撮影する場合は、遺族の許可を取る必要があります。また参列者の中には、写真撮影を不快と感じる人もいるかもしれませんので、あまりたくさん撮影しないようにしましょう。
読経やお焼香の際には、撮影を控える
僧侶が読経している時や、遺族や参列者やお焼香をしている時は、撮影を控えるようにしましょう。どうしてもそのような場面も撮影したいのであれば、他の方の視野に入らないように撮影するようにしてください。故人との最後のお別れの時間になりますので、安らかにお別れできるように配慮する必要があります。
故人に背を向けて撮影をしない
祭壇に背を向けて撮影してしまうと、故人に背を向けてしまうことになります。これは故人に失礼なので、注意してください。
シャッター音やフラッシュに注意する
葬儀のマナーとしてシャッター音やフラッシュに気をつけましょう。シャッター音もフラッシュも故人とのお別れに集中できなくなってしまうだけでなく、周囲に不快感を与えてしまうことになるので注意してください。
SNSへの投稿はしない
葬儀の写真は、遺族が故人との思い出として残したい、参列者の方に思い出として残してもらいたいという気持ちで行われています。そのため、不特定多数の人が見る可能性が高いSNSに投稿することはやめましょう。実際にSNSに葬儀の様子を投稿したことで、トラブルが起こっている事例もあるといわれています。
写真撮影係であることを証明する
参列者が多いほど、写真撮影に対して批判的な声もあるかもしれません。そのようなことを避けるために、写真撮影をする人を決めておき、担当者としてわかるように腕章をつけるというのもひとつの方法です。
葬儀タイプ別の写真撮影に関する注意点
葬儀における写真撮影では、葬儀のタイプ別に写真撮影の注意点があります。ここでは葬儀の種類別の注意点をまとめておきます。
一般葬の注意点
一般葬では、遺族や参列者の意向を配慮した撮影が求められます。写真撮影はできるだけ少なく、タイミングを決めて行いましょう。
家族葬の注意点
身内だけの葬儀なので、写真撮影は比較的自由に行えます。記念撮影として撮影されることも多いです。集合写真が撮影されることも多いです。
社葬の注意点
社葬での写真撮影は、葬儀の記録を残すために行われるので、今後の参考資料となる場合もあります。弔辞・遺族の挨拶・参列者・供花・供物すべてにおいて写真撮影が行われます。
葬儀の写真撮影について注意点をご紹介しました。高松の葬儀場では、写真撮影が可能な葬儀場もあります。写真撮影をされる場合は、プロにお願いすることで、よりキレイに写真に残してもらうことができるので、一度相談されてみてください。