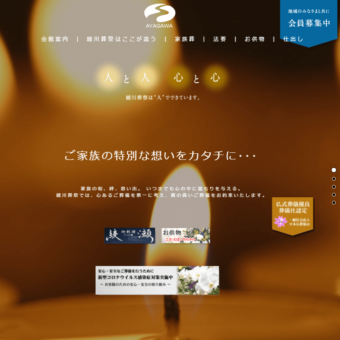葬儀後の食事とは?「通夜振る舞い」「精進落とし」について

葬儀の際、通夜や告別式の後に食事が出されるのは、日本の伝統的な文化の1つです。子どもの頃は、「親に連れられて何となく参加していた」という方も多いのではないでしょうか?この記事では、葬儀に関する食事の種類や内容、故人にお供えする食事、そして礼儀作法について詳しく解説します。
葬儀後のご飯について
「通夜振る舞い」または「精進落とし」として、通夜や法要の後、喪主が僧侶と参列者をもてなすためにご飯を振る舞う習慣があります。それぞれどういったものなのか、具体的に見ていきましょう。
通夜振る舞い
通夜振る舞いはその名の通り、通夜の後に振る舞われる食事のことです。もともとは肉や魚を含まない精進料理が主流でしたが、近年では肉や寿司の入ったオードブルなど手軽につまめる料理が一般的になりつつあります。これは参列者1人ひとりの食べる量や、滞在する時間が異なるためです。
また、都心では通夜振る舞いをせず、参列者に引出物を渡すだけに留めるなど、簡略化する場合もあります。伝統的な儀式ではありますが、特別に定められたルールはありません。なお、通夜に参加した方全員が食卓につくとは限らないので、用意するのは参列者の人数に対し5~7割程度の量が一般的です。お酒も宴会ではありませんので、1人につきグラス1杯程度行きわたるようにすれば問題ありません。
精進落とし
精進落としは火葬後に行われる初7日の法要が終わった後、もしくは火葬をしている間に控室で提供される食事です。そのため、精進落としを口にするのは、火葬に参列した方たちとなります。具体的には遺族や親族、「ぜひ火葬にも立ち会ってほしい」と遺族から乞われた特に親しい友人、そして僧侶です。
通夜振る舞いと違って口にする人数が予め決まっているので、食事はオードブルのような大皿ではなく、1人ひとりに提供されるスタイルが主流です。なお、通夜振る舞いと被らなければ、料理の内容はあまりこだわらなくなってきています。補足になりますが、精進落としは本来、四十九日の忌明けに振る舞われるものでした。しかし現在は簡略化され、火葬後や初7日の法要後に行われるようになっています。
葬儀後のご飯の席でのマナー
葬儀後のご飯、いわば精進落としの場では、いくつか厳格なルールがあります。まず、遺族は僧侶や参列者をもてなすために下座へ、そして宗教者は再上座に着席します。席次は喪主が決めるので、参列する場合はその指示に従ってください。逆に自分が喪主を務める場合は、葬儀社に相談してプランニングしてもらう方法もあります。
着席した後の流れですが、まずは喪主あるいは親族が食事前に挨拶を行います。その後献杯し、食事となりますが、拍手をしたり杯を高く掲げて合わせたりするのはマナー違反です。また、献杯の音頭を取る時も、声が大きくなりすぎないよう、注意しましょう。そして1時間~1時間半後には、締めの挨拶が行われます。
食事中の会話ですが、故人の死に直結する話題は避けましょう。故人の死因はどうしても気になってしまうものですが、通夜振る舞いや精進落としの場で尋ねるのは遺族に対し非常に失礼です。辛い記憶を呼び起こすことにつながるので、絶対に避けましょう。故人の話をする場合は、友人としての楽しいエピソードなど、明るい話題に留めるのが無難です。
また、通夜振る舞いや精進落としは宴会ではなく、あくまで故人を偲ぶ供養や遺族による参列者・僧侶へのねぎらいの場です。そのため、大声で騒いだり、酔いつぶれたりしてはいけません。あくまで神聖な場であることをわきまえて、くつろぎ過ぎないよう行動してください。
葬儀でお供えするご飯
葬儀でお供えするご飯には、枕飯と枕団子の2種類があります。それぞれ役割や意味合いが異なるため、詳しく見ていきましょう。
枕飯
枕飯は故人があの世に旅立つ前に食べる、最後の食事という意味があります。亡くなったら棺に納める前に枕元へお供えし、そして葬儀中も祭壇にお供えするのが一般的です。用意する際は茶碗にすりきり1杯分の米を炊き、茶碗を2つ用意しておきます。そのうち1つは、故人が愛用していた茶碗にしましょう。なお、枕飯に使わない茶碗は、内側を水で濡らしておきます。
盛り付ける際は故人が愛用していた茶碗を下にし、2つの茶碗両方にご飯を押し込みます。上の茶碗を揺らし、ご飯が下の茶碗に落ちたことを確認したら、箸を立てて完成です。この時、ご飯は高く盛られているほど良いとされます。
枕団子
枕団子とは、故人があの世に旅立つ際に持参する、弁当を意味します。お供えする数は、一般的に6個です。これは仏教の教えの1つである輪廻転生の「六道」が由来だという説もありますが、地域によって11個または四十九日に合わせて49個用意する場合もあります。上新粉など、団子を作る際の粉を使って、球体に丸めれば大丈夫です。
飾り方は、6個の場合はまず団子を5個用意し、最後に6個目の団子を中央に乗せます。それ以外の場合は地域によって風習が異なりますので、各地域の風習に合わせましょう。なお、枕団子に関しては、枕飯のように箸を供える必要はありません。
そして最終的には、枕飯と枕団子ともに棺に入れ、一緒に火葬する方式で処分します。この際、故人が愛用していた茶碗は「この世に未練なく成仏できるように」という願いを込めて、割って処分しましょう。
ここまで葬儀後のご飯として通夜振る舞いや精進落とし、葬儀後のご飯の席におけるマナー、そして故人にお供えするご飯について解説してきました。葬儀後のご飯やお供えは、時代や地域の風習に合わせて簡略化されたり行うタイミング、そしてメニューも変わってきたりしつつあります。しかし、枕飯などの文化は日本固有のものであり、古来より受け継がれてきた大事な伝統行事です。そのため、心を込め厳粛な気持ちで臨みましょう。
■お坊さん不在の葬儀はだめなの?手配方法について紹介します
■葬儀の喪主による挨拶。使ってはいけない言葉や挨拶を考えるポイント
■葬儀の日取りはどうやって決めればいい?「六曜」は関係する?
■葬儀の案内状はどうやって書くの?書き方やマナーについて紹介